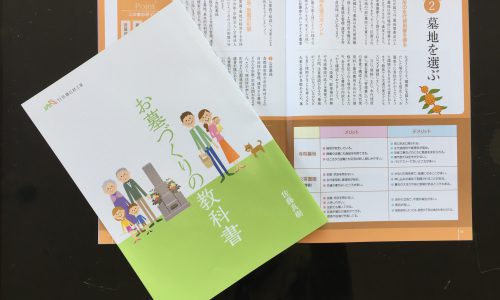昔から「お墓はお寺に建てるもの」というのが一般的でしたが、最近は様々なご事情、お考えから公営霊園を選択される方も増えています。そこで今回は各自治体が管理、運営する公営霊園について詳しくご紹介したいと思います。
仙台市内では「北山霊園」「葛岡墓園」「いずみ墓園」
以前この「宮城お墓相談室」でもご紹介していますが、仙台市内には3つの市営霊園、「北山霊園」「葛岡墓園」「いずみ墓園」があります。現在仙台市民の方がお墓を建てる際に一度は検討するのが「いずみ墓園」のようです。「いずみ墓園」は比較的新しい霊園で環境も良く、またかなりの数の既設墓石(2017年6月時点2万8千基)があります。そのため、他の墓所にお墓を建てる方や東日本各地の石材店が参考に見学に来る、まさにお墓の最先端と言える霊園です。
宮城県内各所に公営霊園はあります
もちろん仙台市内以外にも各所に公営霊園はあります。大きなところでは、石巻の「石巻霊園」や大崎市の「横沢霊園」、大河原町の「原前霊園」。利府町では昨年念願の町営「館山霊園」が造成、貸出になりました。あまりに応募が多かったため、今後追加造成の計画もあるようです。それぞれの公営霊園の詳細は、この「宮城お墓相談室」で順次ご紹介したいと思います。
なぜ公営霊園が人気なのでしょう?
古くからお寺に建てることが一般的だったお墓ですが、なぜ今公営霊園が人気なのでしょうか?もちろんお寺がダメだということではありません。皆さんのお話しを伺っていると「選べる」ということがキ-ワ-ドだと思います。
今はかなり自由にはなっていますが、お寺によってはお墓の形や使用する石材に制約がある場合もあります。そしてなによりもお寺にお墓を建てるということは、そのお寺の檀家になるということを意味します。一度お寺の檀家になると、お子さんやお孫さんなど子々孫々までそのお寺にご供養をお願いすることになるため、将来の可能性を考えてお寺ではない場所にお墓を建てる選択をなさる方が多いようです。
ただしお墓は公営霊園に建ててお寺の檀家になることもできますし、檀家にはならずに納骨や一周忌といった法要だけをご住職にお願いする方も増えてきています。
「永代供養墓」と呼ばれる葬送の形には注意が必要です
最近よく後継者の問題や子供に手間を掛けたくない等の理由で公営の集合墓を希望なさる方も多いようです。よく皆さんこの葬送の形を「永代供養墓」と呼びますが、実際はまったく違うものです。
お寺の「永代供養墓」は共葬の形は同じでも、ご住職が朝夕に読経をして「永代」に「供養」してくれます。一方公営の場合には誰かが御参りに行かない限り「供養」はされません。なので正確には「共葬墓」もしくは「集合墓」が正しい呼び名になり、実質的にはお骨の収蔵設備でしかありません。その違いをきちんと理解したうえで墓所を選ぶことが大切になります。
<まとめ>
お墓は「終の住処」です。どんな気持ちで送りたいか、どんな思いで送られたいか、それをきちんと考えたうえで慎重に墓所は選んで頂きたいと思います。また伝聞や資料だけで決めてしまうのではなく、実際に足を運んでの検討が望ましいと思います。