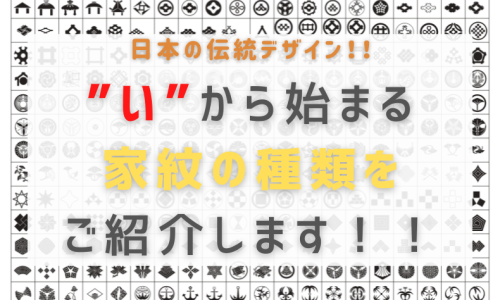お寺のご住職様が読経中に叩く木魚は、丸みを帯びた形がかわいらしくポクポクという音も耳に心地良いですよね。
そもそも、どうして読経中に木魚を叩いているのかをご存知でしょうか?
今回は、見かけることはあってもくわしく知らない、木魚とは何なのかについてご紹介します。
木魚とは?
木魚(もくぎょ)は、読経中に叩く仏具の一種です。
丸みを帯びた木製の大きな鈴のような形をしていますが、以前は本物の魚のように平たい形状をしていました。
かつて中国の仏具が江戸時代に日本へ伝えられた木魚は、クスノキやクワなどの木材が使われており、布や革で先端が包まれたバチを叩いて音を鳴らしています。
禅寺では食事などの集合の合図として、大きな平たい魚板を打ち鳴らす習慣がありました。
この魚板が変化して、現在の丸みを帯びた木魚になったと言われています。
木を彫って乾燥させるため、木魚ができるまでは実に3年~10年という長い期間を要しています。
どうして読経中に木魚を叩くの?
この木魚を叩きながら読経をするのは主に次のような理由があります。
・眠気覚ましのため
木魚が使われるようになった理由の一つが、読経中の眠気覚ましのためという説。
これは木魚のモチーフである魚には、「昼夜問わず目を開けている魚のように、修行僧は常に怠けずに修行に勤しみなさい」という意味が込められているのです。
読経はどうしてもリズムが単調のため、厳しい修行をしている修行僧にとってはつい眠気が忍び寄ることもあるようです。
そこで、木魚を鳴らしながら読経をして眠気対策をしていると言われています。
・リズムをとるため
木魚を同じリズムで鳴らし続けることで、読経のリズムが崩れるのを防いでいるという説もあります。
ピアノなど楽器を演奏するときのメトロノームのように、読経のスピードが安定しやすくなるのだそうです。
・煩悩を吐き出している
かつての平たい魚の形木魚は、口の部分に「煩悩の珠」があしらわれており、木魚を叩くことでその口から煩悩を吐き出していると考えられていました。
つまり読経中に精神統一ができるよう、木魚を叩くことで煩悩をなくしているという説も。
実際、私たちが木魚の音を聞いていても、心が落ち着き厳かな気分になりますよね。
ご先祖様の供養をする大切な法要中は、普段の喧噪を忘れて心を無にできる時間とも言えるでしょう。
<まとめ>
木魚はその見た目も魚だけでなく、龍やヘビなどをモチーフにした、美しい作品が数多くあります。
完成まで長い年月と職人の技術の粋を集めて作る、まさに芸術作品と言えるでしょう。
もし法要に参加する機会があったら、ご住職様が叩いている木魚に少し注目して見てはいかがでしょうか。